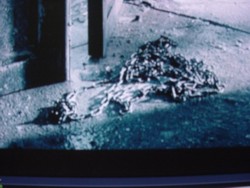X-ray氏作
Sorry Japanese only|
(9)精神病院 ------------------◇I am looking for you.
11月○日(火)8:00p.m. 篤と半田は、発信機の信号を追いかけながら、地図に×印を記入していた。 コンパスを使い、地図を回しながら北に正確に合わせる。 現在位置から、信号を捕らえた方角に、1点目のラインを入れる。 更に200〜300km 移動し、同じように信号をキャッチした方向に、2点目のラインを引く。 この、1点目と2点目の交差する辺りに、発信源があると考えられるからだ。 深い山中の地図であるため、目標物が絞りにくい。 篤のイヤホンから、次第に強くなる電波を追いかけて進んだ。 パジェロのフォグランプだけが、黒い闇を黄色に染める。 突然の訪問者に驚いたように生い茂った木々がざわめき、揺れた。 「ン…半田、かなり強くなったぞ。しかし唐橋先生はなんだってこんな山奥に小西さんを連れ込んだんだ?」 「そんなのこっちが聞きたいよ。あ、タイヤの跡がある。こっちだな」 左のわき道にハンドルを切った。 祈るような気持ちで、闇の中へ手探りで突き進む。 半田が、ライトを一瞬ハイビームに切り替えて、消した。 シルキーホワイトのセルシオは、さびれた建物の前に停められていた。 エンジン停止。 少し離れた林の中に、反射板が光らないように車を横向きに駐車する。 そして、暗闇の中、半田が言った。 「篤、お前はここに残れ。ここまではよくやったと思うけど、満足に歩けもしないお前が行ったところで、何ができる?それよりここで待機して、俺が戻って来なかったときに、麓に下りて警察に連絡してくれないか?」 「嫌だよ!オレは行くよ。這ってでも行く。オレだって小西さんが心配なんだよ」 「携帯も通じない山奥だぞ!何が起きても不思議じゃない。嫌な予感もする」 「大丈夫だよ、オレって悪運強いし。じゃあ、片松葉で行くよ。それなら片手でナイフだって握れる。頼むよ、頼むから連れて行ってくれ」 篤も、自分がわがままを言っているのは分かっている。 半田の言うことの方が、正論だと言うことも分かっている。 しかし、ここまで来て、指を銜えて見ている訳にはいかない。 無言のまま半田が運転席を降り、助手席のドアを開けた。 半田は、篤の腕を自分の肩に回し、懐中電灯を履き替えたばかりのジーンズに差した。
------------------◆Ruins hospital 気温のせいだけとは思えない悪寒が背筋に抜ける。 褐色の雑草の屍骸を踏みしめて奥へと進んで行った。 見上げるその建物は、まるで黒い妖気が立ちこめているようだった。 錆びた有刺鉄線とバリケードで塞がれた入り口。 鉄格子の覗く真っ暗な窓。 朽ちかけた壁や看板から察すると、廃虚となり、十年以上経過しているように思われた。 「鉄格子だ!まるで精神病院みたいだ…おっと」 「大丈夫か?無理するなよ。もっと俺に体重かけていいから」 右側は半田から肩を借り、左側は松葉杖で支えるという、不安定な歩行である。 もちろん街灯ひとつあるわけもなく、半田が翳す頼りない懐中電灯のみが、足元を照らす唯一の道しるべなのだ。 バランスを崩しながら篤は、廃虚病院をにらみつけた。 いよいよ廃虚へと突入だ。 本当にこんなところに小西さんがいるのか? セルシオは何のためにここまで走って来たのか? バリケードで塞がれた正面玄関の脇には、鎖の解かれた小さな扉があった。 二人は肩を組み、逸る心を抑えながら病院内に侵入した。 暗闇。 懐中電灯の明かりがなければ、何も見えないだろう。 重苦しい、澱んだ空気が不安をあおる。 病院らしい受付と長椅子の置かれたロビーを壁伝いに抜けると2基のエレベーターがあった。 その向こうは化粧室だろうか。 人の気配は、まるで感じられない。 それにしても…。 壁に貼られたポスターも、端に停められた車椅子も、処分や整理された様子のない備品や機材も、つい昨日まで利用されていたかのように置き去りにされている。 この病院の終日は、予期せぬ突然の閉鎖だったのだろうか。 1階の突き当りまで来た。 左側頭上には、上り階段が続く。 「3階の鉄格子の部屋はチェックしたほうがいいな」 「ああ」 ここに唐橋のセルシオが停まっている以上、躊躇している時間はない。 しかし、階段を前にして、半田が篤の左肩からするりと腕を抜いた。 「篤、俺が3階見てくるから、ちょっと待ってろよ」 今度は従うことにした。これ以上足手まといで居たくない。 篤を残し、半田は階段を静かに駆け上がった。 暗闇に残された篤は、少し考え、手すりにすがるようにして、ゆっくりと階段を上り始めた。 片足が傷ついているだけで、階段がこれほど苦痛であり、僅か数メートルの歩行が、何十メートルにも感じるなどとは、骨折を経験するまで考えたこともなかった。 「歩くことが出来る」 至極当たり前の行為が僅かにできないだけで、これほど惨めな気持ちになるものなのか? 足手まといかもしれない。 ふと、自分を省みる。 いつからこんな正義感が芽生えたのだろう。 何故、こんな危険に飛び込むのだろう? 仮面ライダーとは言え、あくまで架空の役のひとつでしかない。 しかし、なぜ、痛みをこらえてこの足は進むのだろう。 自分で自分を叱咤し、励ましながら、一歩一歩階段を上っていく。 靴の履けないギプスの指先は汚れ、酷く冷たかった。 ギプスの足が固い床に接地するたびに、足首に刺すような痛みが響く。 先日手術して留めたはずのボルトが外れ、骨が軋むような錯覚が、足を着くたびに起きた。 ああ、彼女は無事だろうか? 怪我などしてはいないだろうか? それでも篤は、麻帆の無事を心から祈った。 2階。 遠くの廊下で、ぼんやりと光が見えた。 誰かいる? 行ってみようか? 半田が向かった3階を目指すべきなのであろうが、篤は単独で2階の探索を行うことにした。 2階へ続く階段の終点の床に、松葉杖を倒して置いた。 こうしておけば、階段を降りてきた半田が気づくだろう。 獣のように篤は、窓側の壁を伝い歩いた。 手を翳しても、その手がよく見えないほど真っ暗な廊下。 その時、少し先の扉が開いて明かりが漏れた。 篤は息を潜め、見守った。 浮かぶ男らしきシルエット。 床にうずくまっていたことが幸いしたようだ。 全く篤には気づかない様子である。 今、確かに誰かが、部屋を出て、篤と反対方向に消えていった。 今の影は、唐橋だったのだろうか? 篤は意を決し、明かりの灯る扉の前まで這うように進んだ。 今すぐ、犯人が戻ってくるかも知れない。 それならそれでもいい。 もしかしたら、この奥で、小西さんが泣いているかもしれないから。 薄明かりが灯るドアノブを、立ち上がり回した。 「あっ…」 ドアの向こうに篤は、信じられないような光景を見た。 -------------------◆Mental hospital
3階。 足音を忍ばせて、ここまで上りついた半田だった。 半田は、精神病院に放射線技師のバイトで行くことがあった。 鉄格子のない窓、日光の入る部屋、ゆったりしたスペース。 建て替えを機に、暗いイメージから脱皮する精神病院が増えてきたと言う。 不祥事続発の舞台から、安心できる医療の場に変わろうとしている。 半田が訪れたのは、そんな真新しい病院であった。 ストレス社会に反映して、近年では精神科にかかる患者も増加の傾向にある。 日本全体の精神病院の入院患者数は、約33万人と言われている。 しかし、実際にはまだまだ昔のイメージどおりの「きちがい病院」も多く存在することは明らかであり、犯罪者、狂人などと一般の人々から強い偏見をもたれているのも現実である。 「精神病院=恐ろしいところ」というイメージを持つ大人が多いのは、訳がある。 1970年、日本精神神経学会が、精神病院の実態調査報告を学会誌に発表した。 看護人が患者を撲殺、リンチするなどの事件の多発などを伝えた。 続いて朝日新聞の夕刊で「ルポ精神病棟」が開始され、悪臭と寒気に包まれた監禁室(現在の保護室)、電気ショック療法がリンチに使われている話など、信じがたい事実をセンセーショナルに連載された。 栃木県内の精神病院で起きた火事は、病舎のひとつが全焼し、患者17人が焼死するという悲劇が起きた。 その遺体の多くが、鉄格子にすがるようにして倒れていたと言う。 また、別の精神病院では、介護職員が患者2名を金属バットでリンチ死させたという事件の発覚。 患者の隔離など、記事の影響はそのまま精神病院のイメージを固めてしまったのだ。 精神病院は医師数、看護職員数(正看、准看)の特例があり、一般病院の場合は6人必要となる場合も、精神病院の場合は2人でよい計算となる。 つまり精神病院の場合は、少ない看護婦で多くの患者を看ることができるのだ。 一部の病院の当時の患者の入院生活は、本当に人権の存在しない酷いものだったらしい。 (平成13年3月の医療法の一部改正により、一般病院のうち療養病床は看護職員1人が6人の患者を、一般病床では3人の患者を看ることになった。また、単科精神病院では看護職員1人が4人の患者を看ることになった。ただし、当分の間、看護職員1人が5人の患者を看ることができる。) この廃虚と化したこの病院は、まさにその時代を反映した精神病院だったであろうと考えられた。 半田の細い懐中電灯の光は、刑務所よりも悲惨とも思える保護室…いや、監禁室と呼ぶのがふさわしいコンクリートの牢獄を映し出していた。 狭く冷たい監禁室。 部屋というよりは、動物園の檻の方がはるかに近い。 正常な人間でも、ここで時を過ごすうちに精神に異常を来たしてしまうのではないだろうか? 扉さえ存在しない便器には、赤黒い血のような染みがべったりと付いていた。 当時の檻の中は、一切の人権が存在しない空間なのである。 半田は幼い頃、悪さをするたびに母親に叱られた台詞を思い出した。 「いい子にしていないと、精神病院に入れちゃうわよ」 意味も分からず「怖い」と思ったような記憶があるが、母親が言わんとする精神病院を目の当たりに見て、今、それがようやく納得できた。 細長い廊下が続く。 規則的に並ぶ幾つもの鉄製スライド扉は、施錠されずに開け放たれていた。 半田が3番目の監禁室を覗いたとき、かすかな物音が遠くで聞こえることに気づいた。 やはり、誰かいるのか? 半田の心臓は鋼のように早まった。 念のため懐中電灯を消して、音がする奥へ向かい、壁つたいに歩いた。 鍵? 半田の靴先が、チャリンと音を立てて、鍵束のようなものに触った。 高まる緊張感。 なぜこんなところに? 誰かが落としたのだろうか? 半田は、すばやく鍵束を拾い上げるとポケットにねじ込んだ。 音は確実に接近していた。 間違いなく、奥の牢から擦れるような音が聞こえた。 慎重に足音を消すように近づき、音がした牢の扉に手を掛けた。 ガシャン 鍵が掛かっていた。 半田は辺りを見回すと、再び懐中電灯を点灯した。 そのとき! 「半田か?遅かったじゃねぇか」 檻の中から、少し苦しそうな、かすれた男の声がした。 -------------------◆The dead body
篤が、見たものは…。 そこは、小さな病室であった。 不規則に4台のベッドが置いてあり、そのうち3台のベッド上には、裸体の女性がそれぞれマットレスに寝かされていた。 明かりは、カーテンの奥、ガラスの観音開きの扉で繋がる隣室から漏れて来るようだ。 一歩足を踏み入れたとたん、腐敗臭にも似た生臭い臭気が鼻をついた。 血のり? どの女性も、特殊メイクを施したように、血のりがべったりと全身にこびりついている。 まるで人形のように。 そして、近づくにつれ目を覆いたくなるような女性たちの姿に吐き気を覚えた。 足の痛みも忘れ、しばし立ち尽くす篤。 落ち着きを取り戻すと、更にはっきりとしたその全貌が浮かび上がる。 手前のベッドの女性は、両足、右手にギプスがはめられていたが、どの部位のギプスも、赤黒い血液で染まっていた。 そして気味の悪い大きな縫い傷と、全ての内臓を抉り出したかのような、薄っぺらな腹部。 中央のベッドの女性は、見覚えがあった。 その顔は、間違いなくM記念病院、整形外科に勤務する前田順子看護師であった。 彼女は、胸部が、何か詰め物をしたように、皮膚をひきつらせて大きく膨らんでいた。 裂けたままの腹部からは、腸がはみ出している。 そして、左足にギプス。 奥のベッドの女性は、顔面が血だらけで、確認は出来なかったが、恐らく最初に行方不明となった、看護師の笹岡香であろう。 同じように、左足に長いギプスが巻かれ、腹部を傷つけられていた。 どす黒く変色した皮膚の色が、時間の経過を想像させる。 4つ目の横向きに置かれた無人のベッドは、麻帆の身が危険であることを篤に伝えた。 もしかしたら、もしかしたら。 あの、明るいカーテンの向こう側に、麻帆がいるのではないのか? 「こ、小西さん」 震える声で呼びかけた。 返事はない。 遺体をなるべく見ないようにして、ベッドの縁を伝い、奥へと向かう。 ガラスの観音扉は音もなく開いた。 もわっと暖かい空気が広がり、ロウソクの溶ける匂いが充満していた。 狭い手術室。 はっ!! 思わず息を呑んだ。 篤の視線の先には、手術台。 揺らめくオレンジの炎が、横たわる女性の輪郭を柔らかく映し出した。 ついに篤は、麻帆を見つけた。 ◆next◆ |
|---|